- 現在のページ
-
- ホーム
- 子育て・教育
- 子育て
- サポート
- 子育て中の方へのお金などのサポート
- 児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当とは?
児童扶養手当とは、父もしくは母と生計を同じくしていない児童や、父もしくは母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

児童扶養手当の受給資格について
次のいずれかに該当する児童を監護する母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、または父や母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、児童を監護し、生計を維持している祖父母等)が受給できます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母が生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母がDVにより裁判所からの保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合であっても次のいずれか該当する場合は受給することができません。
- 父、母、養育者または児童が国内に住所を有しないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 父または母と生計を同じくしているとき(ただし、その者が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は除く)
- 父の配偶者もしくは母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にあるものを含み、政令で定める程度の障がいの状態にある場合は除く)
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)
この場合の児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいのある場合は20歳の誕生日の前日まで)です。
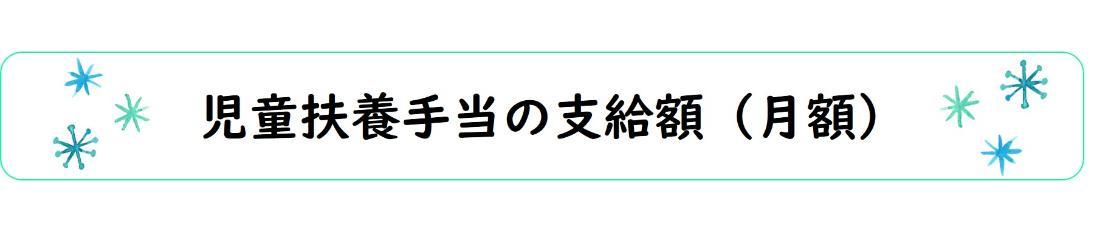
児童扶養手当の支給額(月額)は下表のとおりです。
| 区分 | 全部支給 | 一部支給(所得に応じて決定) |
|---|---|---|
| 児童1人のとき | 月額46,690円 | 月額46,680円~11,010円 |
| 児童2人目の加算額 | 月額11,030円 | 月額11,020円~5,520円 |
| 児童3人目以降の加算額 | 2人目加算と同額 | 2人目加算と同額 |
(令和7年4月1日現在)
- 一部支給は所得に応じて10円単位で設定します
- 手当額は、物価変動等の要因により改定されることがあります。
- 申請者および児童が公的年金等(障害基礎年金等の一部を除く)を受給していて児童扶養手当額の方が高い場合、差額のみの支給となります。
- 毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度とし、年度単位で手当の額を決定します。
- 毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認したうえで、11月以降の手当の額を決定します。
児童扶養手当法の改正Q&A(障害年金等とあわせて受給する場合)PDF厚生労働省
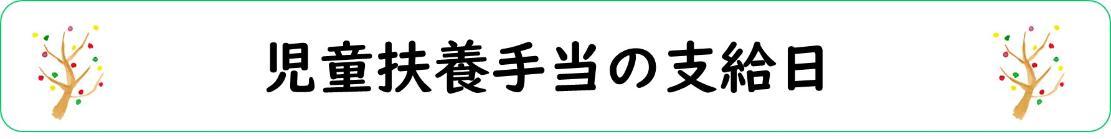
児童扶養手当の支給日は、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に前2カ月分を指定された口座へ振り込みます。11日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日に支給します。
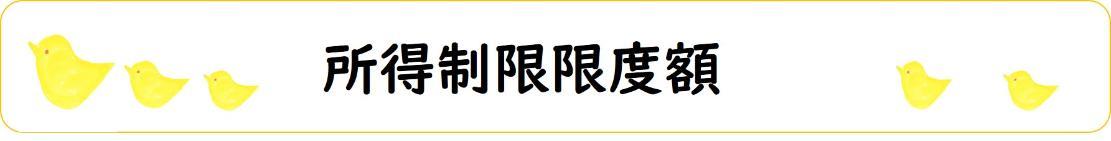
所得制限限度額とは、所得による支給制限があるため、申請者本人または配偶者及び扶養義務者(同居の両親、兄弟姉妹等)の前年の所得額(1月から6月までの間に請求するときは前々年)により全部支給の人、一部支給の人、全部支給停止の人に分かれます。
手当を申請する方(孤児等の養育者を除く)の児童扶養手当においての所得額が、下表の「全部支給」となる「所得制限限度額」を超えていない場合は、全部支給となり、「所得制限限度額」より高い場合は、手当が一部支給となります。「一部支給」となる「所得制限限度額」より高い場合は全部支給停止となります。
また、同居している(住民票上同一世帯である場合のほか、別世帯であっても実態として同居の場合を含みます)扶養義務者等のうち1人でもその所得額が「扶養義務者、配偶者等」の「所得制限限度額」より高い場合は、全部支給停止となります。扶養義務者等には一部支給の制度はありません。
| 税法上の扶養人数 |
請求者本人 全部支給 |
請求者本人 一部支給 |
扶養義務者 配偶者 (父又は母障がいの場合) 孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
| 3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
| 4人 | 221万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 |
扶養親族が5人以上の場合、1人につき38万円を加算した額となります。
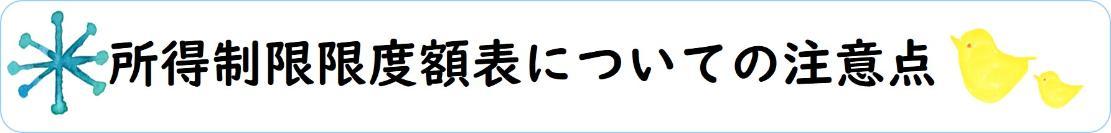
扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系親族及び兄弟姉妹)です。
- ここで「孤児」とは「父母の死亡した児童」をいいます。
- 離婚した後の児童の監護をしない父又は母の所得は、所得制限の対象とはなりません。
- 養育者で受給される場合も「請求者本人」の所得制限となります。
- 収入額はあくまで目安であり、実際の取扱いは地方税法上の控除について、定められた額を控除した後の所得額で決まります。
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と表1の額を比較して、全部支給、一部支給、全部支給停止のいずれかに決定されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。(平成22年度の税制改正において、16才未満の扶養控除の廃止及び16から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されていますが、手当額へ影響を与えないよう扶養控除の廃止がなかったものとして、所得判定を行います。)
- 本人の場合は、
ア) 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
イ) 特定扶養親族1人につき15万円 - 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
- 本人の場合は、
- 寡婦(寡夫)控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)のうち一定の要件を満たす方は、申請により児童扶養手当の所得の算定に当たり、寡婦(寡夫)控除を受けている方と同様の控除が受けられます。
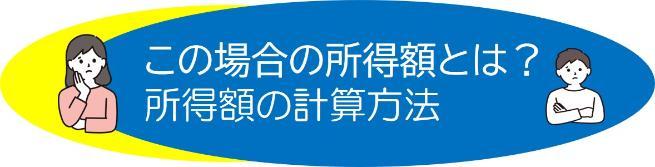
この場合の所得額とは?以下の計算式で算出されます。
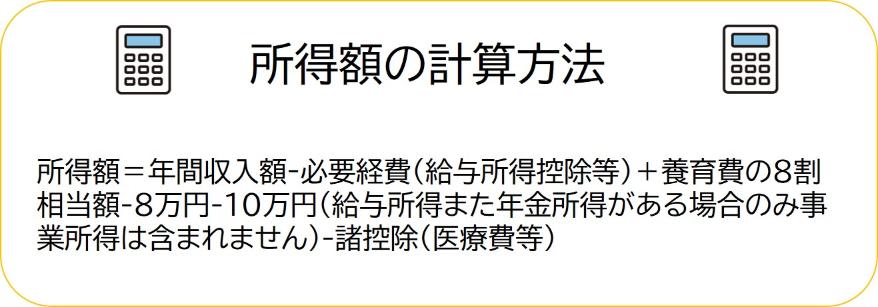
所得額は年間の収入額から必要経費(給与所得控除等)を引き、養育費の8割相当額を足し、社会保険料、生命保険料、損害保険料等の相当額として一律に8万円を引き、さらに、給与所得または年金所得がある場合(この場合事業所得のみの場合は含まれません)は、さらに10万円を引き、医療費控除などの諸控除を引いた金額が所得額となります。

【養育費とは?】
- 児童扶養手当の受給資格者が監護している子どもの父または母から支払われたもの
- 受取った者が受給資格者または子どもであること
- 父または母から受給資格者または子どもに支払われたものが金銭、有価証券(小切手、株券、商品券など)であること
- 父または母から受給資格者または子どもへの支払い方法が、手渡し、郵送、受給資格者または子ども名義の銀行口座への振込みであること
- 養育費、仕送り、生活費、自宅などのローンの肩代わり、家賃、光熱費、教育費など子どもの養育に関係のある経費として支払われていること
【諸控除】控除項目および控除額は下記のとおりです。(令和6年11月現在)
| 控除項目 | 控除額 |
|---|---|
| 障害者控除 | 27万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
| 雑損控除 | 当該控除額 |
| 医療費控除 | 当該控除額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
| 配偶者特別控除 | 当該控除額 |
| 寡婦控除(養育者・扶養義務者のみ) | 27万円 |
| ひとり親控除(養育者・扶養義務者のみ) | 35万円 |
(注意)児童扶養手当の所得計算上は、受給資格者が母の場合は寡婦控除・ひとり親控除が、父の場合は、ひとり親控除は適用されません。

申請時の状況により異なりますので、必要な書類等を確認・相談の上、手続きをしてください。手当は、受給資格および手当額について認定を受けた後、受給することができます。
- 手当は申請した翌月分より対象となりますので、お早めに手続きしてください。
- 認定請求の審査には約1~3カ月かかりますのでご了承ください(提出に必要な書類に不足がある場合、認定までにさらに時間がかかりますので必要書類はお早めにご提出ください。)
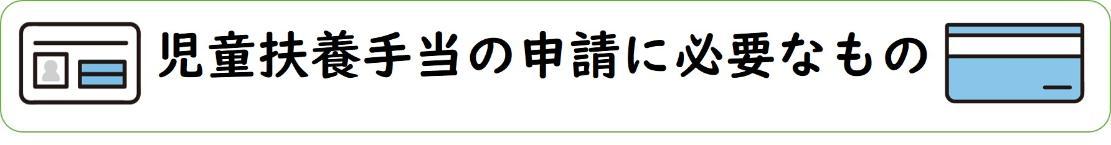
児童扶養手当の申請に必要なものは、申請者本人の状況により異なりますので
必ず事前にご相談ください。
|
戸籍謄本 本人・児童 |
請求時点で交付から1カ月以内のもの 離婚・死亡の事由で申請の方は離婚日・死亡日、配偶者の氏名の記載のあるもの (注意)コピーは不可。必ず市区町村が発行した謄本をご提出ください。 (注意)取得時に戸籍担当課へ児童扶養手当で使用する旨お申し出ください。無料になる場合があります。 |
|
受理証明書 |
戸籍に離婚・死亡の記載がされるまでに時間がかかる場合は、代わりに離婚届・死亡届受理証明書で申請可能です。 (注意)その場合は、後日、戸籍謄本の提出が必要です。 (注意)戸籍謄本をご用意できる方は受理証明書は不要です。 |
| 申請者の身元確認書類 |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など |
| 申請者の個人番号確認書類 |
個人番号(マイナンバー)記載の住民票 マイナンバーカード、通知カード (注意)認定請求書にマイナンバー(個人番号)を記入する欄がありますのでご用意ください。 |
| 普通預金の通帳 |
申請者名義で開設したもの (注意)児童扶養手当の振込口座となりますのでご用意ください。 (注意)口座名義の氏名変更などは早めにお手続きください。 (注意)申請に間に合わない場合、後日でも可。認定までにご提出ください。 |
| その他 |
申立書(事実婚解消・養育・遺棄・別居監護・住所要件など) 民生委員の証明を受けたものや所得の申告控えなど 状況により異なります。(必ずご確認ください) (注意)申請時点では、すぐに用意できないものがありますので後日でも可。認定までにご提出ください。 |
|
所得の申告 本人・扶養義務者 |
手当額等を算出するために必ず申告が必要です。 たとえ扶養として申告している場合でも場合によっては申告が必要になることがあります。 |
| マイナ保険証等 |
ひとり親家庭等医療費等助成を希望する方は必要です。 児童扶養手当のみ請求の方は不要です。 |
申請に必要なものは申請者の状況により異なります。
ご案内いたしますので必ず窓口にてお早めにご相談ください。(予約は不要です)
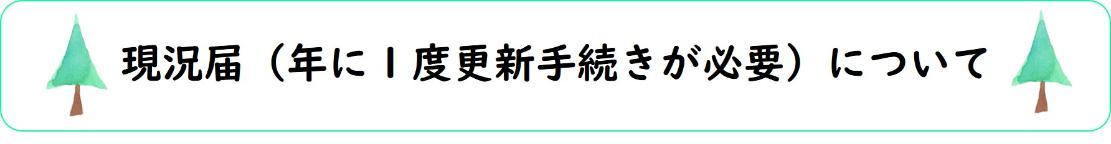
手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届は毎年8月1日現在の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給するための要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を確認するためのものです。現況届の手続き案内通知を前もって郵送いたしますので、受給者本人が手続きを行ってください。R6年8月より一部の方を除いてオンライン申請も可能となりました。窓口での申請についてはオンラインでの予約が必要となります。くわしくは、お問い合わせください。現況届の提出がない場合、11月分以降の手当が差し止めとなりますのでご注意ください。また、現況届の提出を、2年間行わなかった場合、児童扶養手当法第22条の規定により手当の支給を受ける権利が時効により消滅し、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。
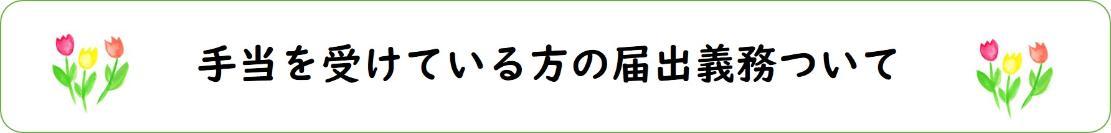
【手続きは必ずご本人が行う必要があります】
主な手続きは以下のとおりです。必要な手続きをしない場合は手当が受けられなくなります。
- 手当額の改定の請求及び届出…監護や養育する児童が増加、減少したとき。
- 支給停止に関する届出…受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟など)と同居することになったとき、または別居することになったとき。また、年金等を受け取れるようになったときなど。(公的年金等受給状況届)
- 現況の届出…毎年8月1日から8月31日までの間に、所得や同居者の状況等を届け出るものです。この届出がないと、11月分以降の手当が受けられません。また、2年以上届出がない場合、時効により支払を受ける権利がなくなります。
- 障害の状態の届出…受給事由が障害の場合、有期認定期間終了時に診断書等の提出が必要になります。
- 氏名・住所・支払金融機関変更の届出…氏名や住所、振込先銀行口座が変わったとき。
- 証書の再交付の申請・証書の亡失の届出等…手当証書を紛失したり、破損したとき。
- 受給資格喪失の届出…以下に該当し受給資格がなくなるとき。
- ア)受給者である父または母が婚姻したとき(事実婚を含む)。
- イ)父または母(養育者)が、児童を監護(養育)しなくなったとき。
- ウ)児童が社会福祉施設に入所、または里親に委託されたとき。
- エ)拘禁されていた父または母が出所したとき。
- オ)遺棄していた父または母から連絡があったとき。
- カ)受給者または対象児童が死亡したとき。
- キ)その他、支給要件に該当しなくなったとき。
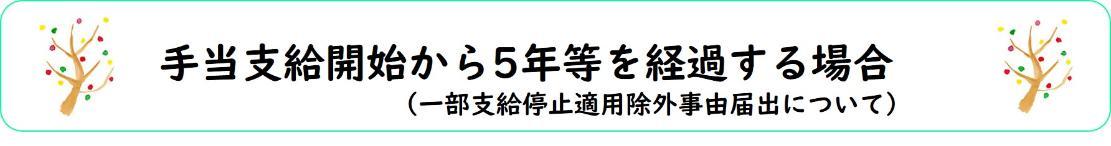
手当支給開始から起算して5年(3歳未満の児童を監護する受給者については、対象児童が3歳に達した月の翌月が起算日)または、支給要件に該当したときから起算して7年を経過したときは、手当の一部が減額されます。
ただし、5年等経過月の末日までの間に、「一部支給停止適用除外事由届出書」及び以下の当該事由を明らかにする書類を提出することにより、適用が除外されます。
- 就業している場合
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている場合
- 身体上または精神上の障がいがある場合
- 負傷または疾病等により就業することが困難な場合
- 監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難な場合
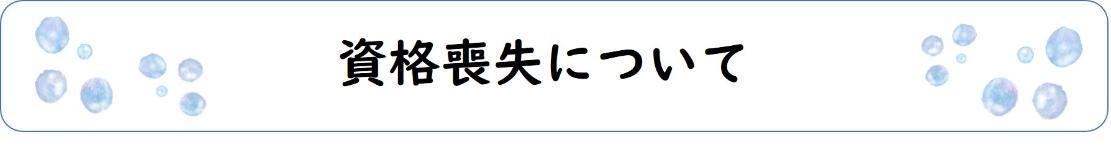
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、届出を行う必要があります。
- 受給者である母または父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
- 受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
- 児童が父(受給者が母または養育者の場合)または母(受給者が父の場合)と同居するようになったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 児童が遺棄していた父または母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- その他、手当を受ける資格がなくなったとき
受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をせずに手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただくことになります。
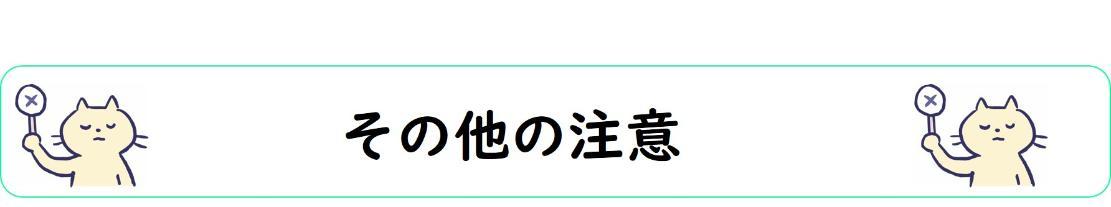
この手当は市民の皆様からの税金で賄われています。偽り、その他不正な手段による受給や届出を怠って手当を受給した場合は、遡っての全額返還や、三年以下の懲役、三十万円以下の罰金に処せられます(法第35条)。
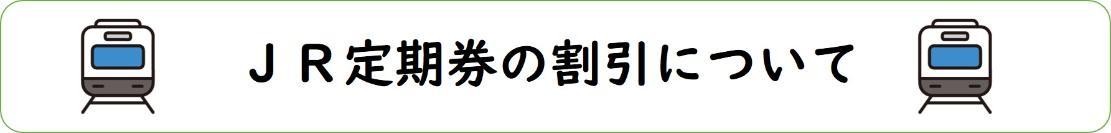
児童扶養手当を受給している世帯に属する方が、JR各社の通勤用定期乗車券を購入する場合に、割引になる制度です。
【JR定期券申請に必要なもの】
- 購入者の写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートルの大きさで、6ヶ月以内撮影のもの)
- 印鑑
- 児童扶養手当証書
- 郵送を希望する場合、宛名を記入した封筒と110円切手
- (注意)児童扶養手当が全部支給停止の方は申請できません。
- (注意)駅の区間や購入する月数によっては、本制度よりも他の制度(学割など)を利用して購入したほうが安い場合があります。
- (注意)申請を受付してから審査があるため、資格証の交付までに約2週間ほどかかります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部こども政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
子育て給付係電話番号:0438-23-7243
未来サポート係電話番号:0438-42-1426
ファクス:0438-25-1350
こども未来部こども政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2025年04月21日